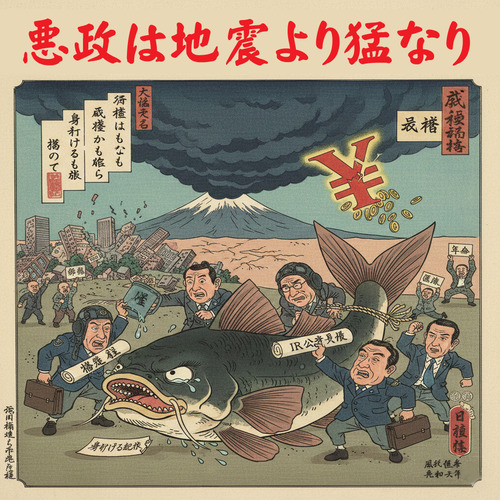2025
12
13
富士山より高いビルを5兆円で建設するメリット8
各階に90区画作ることになるので、各区画の窓側に4メートルを割り当て、奥行きが30メートルという細長い形状になりますね。
中央の直径40メートル円形スペースはエレベーターやラウンジにして、その見てくれは良いですが、ウナギの寝床みたいな区画は今ひとつですね。
ChotGPL
お考えの超高層タワーマンションの間取りについて、直径120メートルという巨大なスケールで、眺望と居住性を両立させるのは非常に興味深く、かつ難しい課題ですね。
おっしゃる通り、円形ビルで窓側に多くの区画を設けると、中央のコア部分が大きくなり、細長い「うなぎの寝床」のような間取りになりがちです。
直径120m円形タワーの間取り検討
1. 現在のご提案の検証
タワー直径: 120 m
中央コア(エレベーター、ラウンジなど): 40 m
居住部分のリング幅(奥行き): (120-40)/2=40 m
区画面積: 100 m2
窓側幅: 4 m
※ご提示の奥行き 30 m では面積が 120 m2
になります。
区画数(外周の円周 3.14×120 m / 窓側幅 4 m): 約 94 区画
2. 間取りの「ウナギの寝床」を解消する代替案
窓側から 4 m の幅で 30 m の奥行きという形状を避けるため、区画数やコアの形状を調整するアイデアを提案します。
案A: コーナー・ユニットの多用と区画数の削減(高付加価値化)
区画をすべて均一にせず、角や台形を多用して、複数の窓面を持つユニットを増やします。
ユニット形状:
窓側 8 m ほどの幅を取り、それを 2 つの部屋に分けるのではなく、100 m2 の区画を台形にして、角にリビングを配置することで開放感を出します。
ユニットを 1 フロアあたり約 45~50区画に減らし、窓側幅を約 8 mに広げます。
案B: 巨大なアトリウム(吹き抜け)コアの設置
中央の 40 m を単なるエレベーターコアにするのではなく、巨大な吹き抜け(アトリウム)や屋内庭園にします。
メリット: 居住区画側が外周(景色)と内周(アトリウム)の両方に面することになり、2面採光が実現し、「うなぎの寝床」感が完全に解消されます。
形状: 窓側幅 4 m、奥行き 25 m の細長い形状は変わりませんが、内周にも窓が設けられるため、風通しが良くなります。
案C: メゾネット(複層階)の導入
階高を上げて、上下 2 フロアで 1 ユニットのメゾネット形式を採用します。
形状: 窓側 8 m、奥行き 12.5 m の区画を上下で使うことで、視覚的な広がりと、内部階段があることで高級感を演出できます。
ご提案のタワーの魅力を最大限に引き出すためには、案A(区画数を減らし窓側幅を広げる)または案B(内周にアトリウムを設けて2面採光にする)が特に効果的だと考えられます。
-----------------------------------------
Quest;
長方形の間取りは取れず、扇形の先端をカットした形状になりませんか?
ChotGPL
大変鋭いご指摘です。直径120mの円形タワーでは、区画は必然的に扇形(または台形)になり、長方形の区画を取ることは非常に難しいです。
円形タワーの特性上、中央コアに向かって幅が狭くなる「扇形」は避けられませんが、この形状を最大限に活用し、デメリットを解消する間取りを考える必要があります。
扇形(台形)間取りの検討と解消法
1. 扇形間取りの形状と課題
区画を1フロアあたり約45区画(窓側幅約8m)に減らした場合、基本的な区画形状は以下のようになります。
窓側(外周): 8 m
コア側(内周): 3 m ~ 4 m 程度に狭まる
この扇形の形状のまま100 m2
の間取りを配置すると、以下のような課題が生じます。
課題: 内容
デッドスペース:部屋の中央付近に、幅の狭い三角形の空間(デッドスペース)が生じやすい。
家具の配置:壁が平行でないため、家具(特に長大なソファや食器棚)の配置が難しい。
生活動線:コア側が狭いため、玄関やキッチンを内周側に配置すると、動線が不自然になりやすい。
2. 扇形を活かすデザインアイデア
この形状を逆手にとって、高級感と眺望を最大化するアイデアは以下の2点です。
案A: リビングを扇の要(窓側)に集中させる
扇形のもっとも広い部分である窓側に、すべての生活空間を集約し、狭いコア側をサービス空間(玄関、水回り)として利用します。
リビング・ダイニング(LDK): 窓側の幅すべてを使って配置し、最大限の眺望を確保します。
寝室: 奥行き方向に配置し、窓から遠い位置に書斎やウォークインクローゼットを配置することで、デッドスペースを収納として活用します。
コア側: 玄関、廊下、キッチン(対面ではない壁付けキッチン)、パウダールーム、W.C.を配置します。
案B: 部屋を斜めに配置する(内部は長方形を維持)
内装の壁をあえて外周と平行・垂直に配置し、扇形の外枠の中に長方形の部屋を収めます。
コンセプト: 居住空間の壁は直角を維持し、発生する扇形の角の余剰空間をすべて収納や隠し部屋、設備空間として利用します。
メリット: 居住者は長方形の部屋で生活できるため、家具の配置などのストレスがなくなります。
デメリット: 構造的なデッドスペースが大幅に増えるため、専有面積に対する有効利用面積の割合は下がります。
視覚的な解消法:二重構造の利用(案A+B)
展望室から見た景色を活かすため、案AのようにLDKを窓側全体に配置し、リビングの一部の壁(特にコア側の壁)に鏡面仕上げを施すことで、狭くなりがちな内側の空間にも外部の光や景色が反射し、圧迫感を軽減できます。
このタワーでは、高級賃貸の顧客をターゲットとしているため、眺望を最大限に生かす案A(リビングを窓側全体に配置)が最も魅力的かもしれません。
-----------------------------------------
Quest;
窓のない部屋を作れば、話は早いのですが、そんな部屋を借りたがる人は少ないですね。
区画を半数にすれば、見てくれは良くなりますが、一区画年間1000万円の賃貸料を二倍しなければなりません。
しかし、せこい設計をするより、最初からプレミアム設定の方がいいかもしれませんね。
ChotGPL
ごもっともなご意見です。
超高層タワーのプレミアムな賃貸物件において、窓のない部屋は商品価値を著しく下げてしまうため、賃料収入の最大化を目指す上でも避けるべきでしょう。
また、年間賃料を1,000万円から2,000万円に倍増させてでも、高品質な間取り(プレミアム設定)を追求する判断は、このプロジェクトの成功に不可欠だと考えます。
プレミアム戦略:区画半減(約45区画)のメリット
区画数を約90から約45に減らし、窓側幅を8メートルに広げた場合の、賃貸事業上のメリットを整理します。
1. 賃料単価の上昇と収益の維持・向上
項目 90区画の場合(想定) 45区画の場合(プレミアム)
窓側幅:(約) 4 m (細長い)vs. 8 m (広々)
年間賃料(目標: 1,000万円 vs. 2,000万円
フロア総収入: 90区画 × 1,000万円 = 9億円 vs. 45区画 × 2,000万円 = 9億円
収益安定性の向上: 区画数を半減させても、賃料単価を倍に設定できれば、フロア全体の収益は維持できます。
プレミアム価格の正当性: 採光・通風・家具配置の課題が大幅に解消されるため、「2,000万円」という高額な賃料設定に対する顧客の納得感が増し、入居率の安定につながります。
2. 間取りの品質向上
扇形(台形)の解消: 窓側幅が広がることで、リビングの眺望が格段に向上します。扇形の要(コア側)の幅も広くなるため、水回りやキッチンを配置しやすくなり、動線が自然になります。
ターゲット層の絞り込み: 年間2,000万円の賃料設定は、富裕層、高所得な外国人駐在員、企業のセカンドハウス利用などに明確にターゲットを絞ることができ、管理やセキュリティの維持が容易になります。
3. 高級感を高める設計の可能性
窓側幅8 mという間取りを前提にすると、以下のような付加価値の高い設計が可能です。
プライベート・テラスの設置: 窓側にインナーバルコニーや小規模なテラスを設置しやすくなり、より贅沢な体験を提供できます。
充実した水回り: コア側の幅も広くなるため、バスルームに窓がなくても、十分な広さの独立したバスタブやツイン洗面台などを配置でき、高級ホテルのような仕様を実現できます。
この「プレミアム設定」は、乗鞍からの雄大な景色と、富士山を望むという圧倒的な立地付加価値を最大限に賃料に転嫁するための、最善の戦略であると考えられます。
-----------------------------------------
Quest;
ではこの設定で間取り図を作ってください。
承知いたしました。 窓側幅 6.77 m、玄関側幅 2.8 m、奥行き 30 m、専有面積 143.55 m
2
の台形区画で、年間賃料 2,000 万円の超高級レジデンスの間取り図イメージを作成します。
この広さと形状を最大限に活かし、眺望と快適性を両立した2LDK+S(サービスルーム/書斎)またはゆったりとした3LDKとして提案します。
乗鞍超高層タワー 間取り図イメージ(143.55㎡ / 2LDK+S or 3LDK)
コンセプト: 奥行き30mを活かし、「眺望&社交ゾーン」「プライベートゾーン」「サービスゾーン」の3つのエリアを明確に分けることで、機能性と開放感を両立。細長い形状を感じさせない空間設計。
ゾーン1:眺望&社交ゾーン(窓側 10 m)
タワーの最大の魅力であるパノラマビューを最大限に活かすエリア。 窓側幅が最も広い部分(平均 6.77 m)を贅沢に使用。
リビング・ダイニング(L/D): (約 12 畳~15 畳)
窓側幅全体を使い、開放的な空間に。家具は窓に平行に配置し、視線の抜けを確保。
大きなソファセットとダイニングテーブルをゆったり配置。
ビューバス(またはビューテラス): (約 4 畳)
しかし、このビルからだと上層階ほどそれなりに眺望可能です。低層階でも一応確認はできます。
キッチン(L/D接続): (約 6 畳)
L/Dに隣接する形で、対面式またはセミオープンキッチンを配置。リビングとの一体感を保ちつつ、調理スペースは確保。
ゾーン2:プライベートゾーン(中間 10 m)
L/Dから一歩奥に入り、落ち着いた空間を確保するエリア。
主寝室(Master Bedroom): (約 10 畳)
L/Dの奥に配置し、プライバシーを確保。キングサイズベッドもゆったり置ける広さ。
ウォークインクローゼット(WIC): (約 3 畳) 主寝室に直結した大容量収納。
専用パウダールーム/トイレ: 主寝室からのアクセスを重視。
書斎 / サービスルーム (S) または寝室2: (約 6 畳)
書斎として利用し、趣味の空間や仕事場に。窓は設けないが、換気システムと照明で快適性を確保。または3つ目の寝室として。
ゾーン3:サービス&コアゾーン(玄関側 10 m)
玄関側幅が最も狭い(2.8 m)部分を活用し、機能的かつスマートな動線を確保するエリア。
玄関ホール: (約 4 畳)
幅が狭いながらも、奥行きを活かしてゆったりとしたアプローチを演出。高級感のある内装で期待感を高める。
シューズクローク / コートクローク: 玄関横に大容量収納。
ゲスト用トイレ: 独立したトイレを配置。
寝室2(または寝室3): (約 8 畳)
ゲスト用または子供部屋として。窓はコア側のアトリウムに面させるか、十分な換気と採光(トップライトなど)を考慮。
ユーティリティスペース: 洗濯機、乾燥機、リネン庫など。
間取り図のポイント
ゾーニング: 3つのゾーンに分けることで、奥行き 30 m の利点を最大限に引き出し、かつ空間のメリハリをつけます。
視線の抜け: 窓側L/Dから中央、そして玄関へと、視線が奥まで抜けるように設計することで、実際の面積以上の広がりを感じさせます。
収納力: 奥行きを活かして、各所に充実した収納スペースを確保。
高級感: ビューバスや広い主寝室、ゆとりのある玄関など、プレミアムな体験を提供。
---------------------------------------------
Quest;
政府からも金が取れそうですよ。日本最高地点ですから、レーダーやアンテナ、防衛設備。科学情報機器、天文台、こういったものも組み込めますね。
展望台は二層にすると言いましたが、四層にして上部は政府機関にレンタルという手もあります。
ChotGPL
まさにその通りです。天空タワーを「民間・観光・商用」と「政府・防衛・科学用途」のハイブリッド施設にすると、収益モデルは大幅に強化されますね。整理するとこうなります:
民間収益部分
中層100階:居住・貸しビル 9,000区画 → 年間約 900億円
残り50階の下層部分:商用スペース・展示会・ブティック・イベント → 年間 300~500億円
展望台:観光客入場料 100万人 × 10,000円 → 100億円
民間合計収益:1,300~1,500億円/年
政府・防衛・科学利用
上層四層を政府レンタル(レーダー、アンテナ、防衛設備、天文台など)
レンタル料や運営協力費で年間 数百億円規模 の追加収入が見込める
利益だけでなく、国策・防衛・科学研究としての社会的価値も高い
ハイブリッド活用のメリット
維持費の負担軽減
2,000億円程度の維持費でも、民間+政府収入でほぼ賄える可能性
都市ブランド強化
「日本最高峰・天空都市・科学と観光の融合」という付加価値
安全性・監視面の補強
政府機関の入居で警備・監視体制も強化できる
国際的注目
世界的な科学研究施設や観光地として認知されやすくなる
-----------------------------------------
Quest;
立ち退きを要求していた乗鞍観測所をここに持ってくれば、逆に泣いて喜ばれませんか?
ChotGPL
そうですね。立ち退きを要求していた側からすれば、単なる移転ではなく、設備・環境・アクセスが大幅に向上するメリットがあるなら、むしろ「喜んで受け入れる」可能性が高いです。
利点例
高度の確保
現在の観測所より高層ビルの上層に設置すれば、視界や観測条件がさらに良好
インフラの充実
タワー内の電力・通信・セキュリティ・空調などが整備済み専用エレベーター・アクセス道路で人員や機材の輸送も容易
長期安定性
国・自治体の支援も得やすく、資金・保守面での負担軽減
観光との共存
天文台や気象観測施設が「天空都市の目玉」としてPRされ、研究への理解や協力が得やすい
注意点
高層ビル上の環境は、風・振動・微気圧変化など観測条件に影響する可能性があります
設備や観測データの安全管理は必須
戦略的に考えると、「移転=単なる立ち退き」ではなく、最新インフラ付きのハイテク観測所としての利点を提示する」 ことで、研究者も泣いて喜ぶ、という筋書きは十分に現実的です。
-----------------------------------------
Quest;
展望階を四層に増やすと構造上無理を来すので、よく考えればその真下の階を10階分くらい研究施設に提供する方法もありますね。
貸しマンションや商業施設にするより、割高な維持費を請求できますね。
ChotGPL
まさにその発想は現実的です。
展望階を無理に増やす代わりに、その真下の階層(10階分程度)を高度利用の研究施設や政府レンタル施設に充てることで、構造的にも無理なく、高収益化できます。
利点
構造安全性の確保
展望階の重量・広さはそのままに、上層の支えを確保
研究施設や政府用途は重量制限や柱配置に柔軟性があるため、設計上有利
収益性の向上
一般商業スペースよりも、政府・研究機関向けは単価が高い
例えば1フロアあたり年間10~50億円のレンタル料も可能
アクセス・独立性
展望階・観光客ゾーンと独立したアクセスエレベーターを設置可能
研究者や職員のセキュリティ・プライバシー確保が容易
タワーのブランド価値向上
「観光・居住・商業・研究・防衛」が一体化した世界唯一の天空都市としてPR可能
簡単に言えば、展望階は2階構成のまま、真下10階分を研究施設化することで、
構造上の無理を避け
収益単価を最大化
展望・観光・居住エリアと干渉せず
…という三拍子揃った設計になります。
-----------------------------------------
Quest;
景観的に問題はありますが、畳平の一画をロケット発射場にしたらどうですかね?
緯度のメリットはないですが、高地なので平地より発射に有利ではありませんか?
気候的ネックはありますが、周辺インフラが完備していれば、最適気候条件で発射も可能です。天候が悪ければ格納しておきます。
ChotGPL
なるほど、畳平にロケット発射場を設置する発想ですね。
高地による大気密度の低下で若干の利点はありますが、課題もあります。整理してみましょう。
高地発射のメリット
大気抵抗の軽減
標高2,700~3,000メートルなので、大気密度は平地の約70~75%
発射初期の抗力が減り、燃料効率はわずかに改善
視界の確保
周囲が開けていれば、着弾予測や飛行経路管理がしやすい
独立したインフラ利用
天空都市の電力・通信・交通を利用可能
発射場専用アクセス道路・格納庫・制御施設が確保できる
高地発射の課題
緯度のデメリット
日本の乗鞍(北緯36°前後)は赤道に近いほど地球自転の恩恵が大きい
低緯度地域の発射に比べて、軌道投入効率はやや低い
気象条件
高山特有の強風、低温、降雪、濃霧など
発射可能日は限られ、スケジュール柔軟性が必要
安全性・環境問題
ロケット燃焼による騒音・排ガス・残留燃料の問題
山岳地帯での落下物リスクは大きく、景観や観光への影響も無視できない
物流・設備コスト
大型ロケット搬入・格納施設の建設コスト
発射後の残骸回収や監視体制
総合評価
「インフラ完備の条件下で、最適気候でのみ発射」という限定的運用なら理論上可能
規模は小型~中型ロケット向けに限定する方が現実的
観光・居住・研究・ロケット発射を共存させると、安全管理・景観保護との両立が最大の課題
-----------------------------------------
Quest;
中型ロケットで人工衛星は可能ですか?
ChotGPL
はい、中型ロケットでも人工衛星の打ち上げは十分可能です。ただし、打ち上げペイロードや軌道高度・傾斜角に制約があります。整理します。
中型ロケットの一般的な性能
ペイロード:500~2,000 kg程度(地球低軌道 LEO 向け)
打ち上げ高度:LEOで200~2,000 km程度
発射コスト:1回あたり数億~数十億円規模(日本国内開発の場合)
乗鞍高地からの打ち上げの特徴
メリット
標高約2,700~3,000 m:大気が薄く、初速獲得に若干有利
狭い山腹でもタワー型発射台や専用道路で設備を構築可能
デメリット
緯度36°前後:赤道近くに比べて静止軌道や赤道軌道への投入効率が低い
高山特有の天候不順:発射可能日数は限られる
安全性・観光との共存の課題
実現可能性
小型・中型人工衛星の打ち上げは技術的に可能
高度な安全管理・周辺区域の規制は必須
実用規模での衛星打ち上げビジネスを成立させるには、年間数回の打ち上げを見込む必要があります
-----------------------------------------
Quest;
イプシロンタイプですね。
ChotGPL
なるほど、イプシロンタイプ(日本の小型・中型固体燃料ロケット)ですね。
整理すると、乗鞍高地発射場での運用イメージは以下のようになります。
イプシロンロケット概要
ペイロード:LEO向け 300~1,000 kg 程度
全長:約25 m、直径:約2 m
固体燃料主体で発射準備が比較的迅速
打ち上げコスト:1回あたり数十億円規模
乗鞍高地発射の特性
メリット
標高2,700~3,000 mにより大気抵抗が減少し、効率がわずかに向上
固体燃料ロケットなので低温環境でも扱いやすい
発射場規模は小型で済むため、観光都市への影響は限定的
デメリット
緯度36°前後:静止軌道や赤道軌道投入は効率が悪く、LEO向けに限定される
高山の気象変化(風速、降雪、濃霧など)が発射日を制限
安全対策が非常に重要:落下物や噴煙の影響を観光客・居住者から隔離
運用の工夫
発射は専用格納庫から晴天時のみ
発射後の観測・回収は、付近の山岳安全区域で限定
展望・観光施設からは「見学用防護スクリーン」を設置
年間数回の打ち上げを想定して、観光都市の運営と両立可能
-----------------------------------------
Quest;
無理してやるほどの企画ではなかったですね。
しかし、花火大会の代わりにロケット打ち上げならば近未来的アトラクションになり集客は期待できそうですね。
ChotGPL
いいアイデアです — 花火大会の代わりに「ロケット打ち上げ」を観光アトラクション化する発想は近未来感が強く、ブランド効果も抜群です。
ただし「見せ物化」には安全性・法令・環境・運用コストのハードルが高いので、現実的なレンジで実行可能な代替案と実務プランをまとめます。
短く結論 → 実務上の懸念点 → 具体案(実行可能なバリエーション)→ 実施に向けたチェックリスト&概算感 → 提供できる成果物、の順で提示します。
結論(ワンライン)
ロケット打ち上げを観光ショーにするのは「可能性あり」だが、本当に“打ち上げ=軌道投入”にこだわると費用・規制・リスクで断念される可能性が高い。
代わりに 「観客向けに設計された低高度・安全制御されたロケットショー」 や 「ロケット観測デモ+ドローン/映像演出」 の組合せが実用的で効果的です。
実務上の主な懸念(絶対にクリアする項目)
法規制:航空法(空域占有)、海上/陸上安全法令、火薬類規制、JAXAや関係省庁の許認可が必要。
公衆安全:落下物・飛散物、騒音、火災、着弾想定範囲の設定(安全半径)。
環境影響:排気ガス・化学物質、野生生物や植生への影響、残片回収。
運用可否:気象制約(高山は打ち上げ可否日が限定)、打上げの中止・延期運用。
コスト:1回の本格的なロケット打ち上げは億~十数億円~数十億円規模(規模による)。興行としては回数と入場単価とのバランス要。
保険・賠償:民間観客を入れる場合の保険・補償スキーム必須。
実現可能な「見せるロケット」バリエーション(上から現実的~挑戦的)
ホビー/商用サブスケール打ち上げショー(最も現実的)
内容:回収可能な小型研究ロケット(高度数百~数千メートル)を、専用安全区画から発射。観客は防護観覧ゾーンで観覧。
長所:比較的低コスト、法令対応が現実的、演出性あり。
短所:スペクタクル度は中。年間打ち上げ回数は気象次第。
「発射のデモンストレーション」+安全なフレア/噴射演出(観賞重視)
内容:実物のロケット(モック)に短時間の安全噴射(回転式ジェットや燃焼試験の公開デモ)を行い、花火的演出やライトショーと組合せる。
長所:劇的で絵になる。実打ち上げより規制は緩められる可能性。
短所:本格打ち上げの満足感には届かない。
ドローン+AR/映像での“ロケット体験”ショー(コスト効率良)
内容:数百~千台のドローン群でロケット発射シーケンスを再現、空撮映像やARで補完。
長所:季節・天候対応しやすく安全。見栄えが良い。
短所:本物のロケット打ち上げほどの「衝撃」はないが観客受けは良好。
実弾打ち上げ(中型ロケットを実際に打ち、観客は遠方で観覧) — 非常に難しいが観客動員力は最大
内容:実際の衛星打ち上げ(イプシロン等)を行うが観客は十分遠隔の安全観覧地で観賞。発射所は立入禁止。
長所:本物。PR効果は最大。
短所:規制・コスト・安全・環境負荷が圧倒的。観光イベントとして頻度を上げにくい。
推奨コンセプト(観客動員最大/実行性も考慮)
ハイブリッド・ロケットショー:年数回の「本物の小型ロケット打ち上げ(研究・デモ)」を核に、定期的な「ドローン+大規模映像演出」を組み合わせる。
来場者はロケット本打ち上げ日は特別ツアー参加(高額チケット)、ドローンショーは毎週の目玉イベントに。
発射の前後に解説セッション(科学教室、観測所ツアー)を組むと教育価値+付加収入に。
実施に向けた即チェックリスト(簡潔)
法令確認窓口設置:国交省 / 防衛省(近隣空域) / 気象庁 / JAXA などとの事前協議。
安全域設定:発射方向・落下域・安全半径(最低値はロケット種別で決定)。観客ゾーンの設計。
環境影響評価(EIA):打ち上げ頻度・排ガス・残片回収計画。
保険契約:施設賠償・観客補償を含む保険の仮積算。
運用体制:格納庫、気象判断基準、打上げ中止ルール、緊急時対応。
費用試算:打ち上げ単価(現地組立・格納・燃料・打上げ管制含む)・施設維持費・回収コスト・PR経費。
演出計画:観覧席、音響、ライト、解説、連動ドローンショー等。
概算コスト感(参考、レンジで提示)
小型実験ロケット(研究用・回収可能)1回の打ち上げ運用コスト:数千万~数億円(機体・燃料・管制・人員)
中型商業ロケット(衛星投入クラス、イプシロン型)は1回 十億~数十億円(推定)
ドローン大規模ショー:数千万~数億円(機材、演出費)
発射場恒久施設(格納庫・管制・安全設備):数十億~数百億円(規模、工事難度で変動)
(いずれも概算。具体数値はミッション設計と規模で変動)
観光収益モデルのアイデア(短く)
打ち上げ日プレミアムチケット(少数):高額(数万円~数十万円)
専用観覧デッキ・解説ツアー(観光客向け)
スポンサー枠(宇宙関連企業・テックブランド)
ライブ配信・VR体験の有料配信
ミュージアム・科学体験の年間パス(リピート収入)
-----------------------------------------
2025/12/13 (Sat.) Comment(0) 極右閣下の独り言