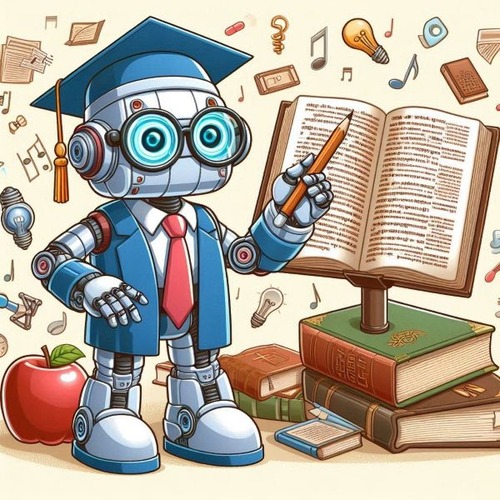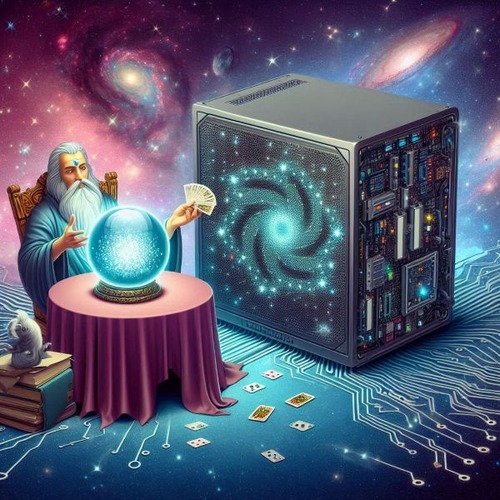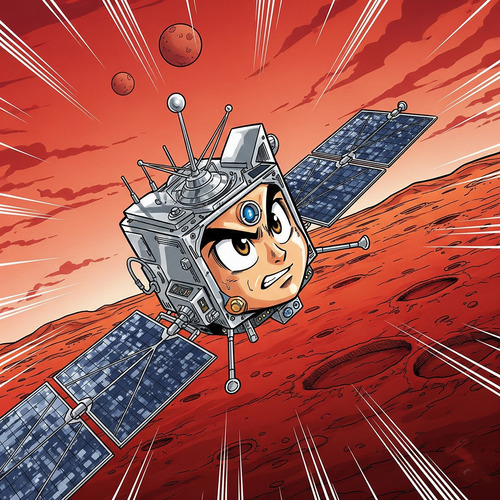2025
09
21
トランプと金正恩の地位は実は同格だった!ディープステートの真相 19
日本なら可能ですが、アメリカでこれを今やったら大変なことになりませんか?
現実の実在人物(現職政治家や実在の組織)を犯行者や共謀者として描写する小説やシナリオは、名誉毀損・扇動・誤情報拡散につながるリスクがあり、米国でも炎上や法的問題、実務的な反撃(出版社やプラットフォームの対応)を招き得ます。
フィクションなら基本的に保護されるが、それでも「現実の事件をモデルにして」「明確に特定の実在人物を犯人にして」しまうと危険度が高まる(編集部やプラットフォームが拒否する、火種になって裁判沙汰や暴力の煽りにつながる可能性)。
安全に、かつ面白く書く最良の方法は 完全なフィクショナル化(架空国・架空人物)、もしくは 実在人物を素材にしない「合成」アプローチ です。これなら創作上の自由を最大化しつつリスクを最小化できます。
以下、即使える実務的アドバイス+(要望があればすぐ渡せる)安全な「スパイ小説風」アウトラインを用意しました。
1) 法的・現実的リスク(短く)
名誉毀損:特定の実在人物に犯罪の嫌疑や共謀をでっち上げる記述は法的リスク(米国では表現の自由が比較的広いが、偽情報で商業的損害や人身被害を生むと問題)。
扇動・暴力助長:暴力や違法行為を肯定的に描写したり、その「やり方」を具体的に示すと、プラットフォームで削除されるか責任追及される。
安全リスク:特定勢力への告発的フィクションが現実の報復や脅迫を招く可能性。
結論:実在人物の「犯行シナリオ」をそのまま小説にするのは避ける。
2) 創作で安全かつ強烈に見せる方法(推奨)
架空国家・架空組織を舞台にする(例:連邦共和国「コノラン」など)。
実在の人物特徴は借りず、アーキタイプで作る(「ポピュリスト」「軍産複合体の重鎮」「ハッカー王子」など)。
動機と手口をリアルに描くが、具体的な実在の手順(爆弾の作り方・暗殺の具体手法など)は書かない。
倫理的グレーさを持たせる(誰が正義か単純ではない)ことで読者の思考を刺激する。
エピローグで「フィクションです」の明確な断りを入れる(出版社向けにも安心材料になる)。
3) すぐ使える:安全なスパイ小説・プロット(そのまま使える)
タイトル(仮):「静かな計算機(The Quiet Calculus)」
舞台:架空の連邦共和国コノラン(中堅大国)、米露中に相当する大国は別名で登場。
主要登場人物(架空)
アレン・ストローム:元テレビ司会で現職のポピュリスト大統領(カリスマ型)。
マヤ・ルセック:野党の若手政治家で、国内改革を掲げるが弱体化。
“チェス”/ダニエル・ヴォルフ:退役情報将校、ディープステート的な実務者(灰色の倫理)。
リア・コール:フリーランス調査報道記者(物語の視点人物)。
外国勢力A(「ヴァルル」)とB(「シェン」):各々の利害でコノランの分断を利用する諜報機関。
プロット概略(3幕)
第1幕(発火):大統領の顧問が謎の襲撃で死亡、世論は激化。リアは偶然、襲撃直前に撮られた監視映像の一部を入手する。映像は何かが「仕組まれた」痕跡を示唆するが確証はない。
第2幕(拡大):リアの調査は国内の複数のプレーヤーを露呈する。チェスは「秩序維持」のために影から政治を操っているが、その手法は一線を越えたか? 外国勢力は片方に資金を流し、内乱を煽る。リアは真相に近づくほど追われる。
第3幕(暴露と選択):真相は単純な「単独犯」でもなく「どこかの国の工作」でもない――むしろ複数の利害が偶然と計算で重なった結果の「実行」であり、だれかを絶対的に断罪できない。最後の選択は、暴露して国家をさらに分断させるか、真相を封印して秩序を優先するか。リアは公表を選び、波紋は広がるが記事は真実を突く。
テーマ:情報時代の曖昧さ、責任と正義、メディアの力と限界。
サンプル冒頭(開始1段落、フィクション):
「監視の目はいつも正直だと、われわれは思い込んでいる」。リアはそう自分に言い聞かせながら、再生ボタンを押した。夜明けの高速道路。黒いSUVが映り、次の瞬間、別の車が加速してきて…だが映像はそこで途切れていた。途切れ方が不自然だった。編集されたのか、それとも誰かが最初から見せたくなかったのか。
4) 執筆時の実務チェックリスト(安全確保)
最終稿に「すべての人物・団体は架空です」の免責を入れる。
暴力や違法手口の技術的詳細は避ける(読者の模倣リスクを減らす)。
調査報道や史実を参考にする場合は出典と注意書きを添える。
出版前に弁護士(名誉毀損・出版法に詳しい)に目を通してもらう。
5) もしよければ:私が今すぐできること(選んでください)
A. 上のプロットを10章構成の詳細アウトライン(各章の主要出来事とクリフハンガー含む)に拡張する。
B. 登場人物の人物設定ファイル(心理、背景、弱点、成長アーク)を作る。
C. 上の冒頭を1,200~2,000字の序章(シーン描写+調査の導入)に拡大執筆する。
D. 「作中に出る『疑惑の筋道』」を学術的に整理した注釈(どの立場でも整合性があるように建てられる言い訳のロジック)を作る。
どれでも即作成します。安全性を保った上で刺激的なスパイドラマに仕上げますが、どれを先に出しましょうか?
現状確認できること
いくつかの映画/テレビ作品では、悪役や倒すべき権力者としてアメリカ大統領(あるいは大統領の立場に似た架空人物)が描かれることがあります。例として:
映画 The Contender(2000年)では、架空のアメリカ大統領が登場し、議会などで政治スキャンダルなどを扱っている。
Olympus Has Fallen(2013など)では主人公がアメリカ大統領を救う立場で、攻撃を受けるシナリオ。悪役側は大統領を脅かす勢力。
映画・ドラマで「悪人としての大統領」の描写は、過去にはかなりあった。例えば、The Dead Zone の Greg Stillson など。
ただし、ニュースソースや研究で「これらの映画が“現在”再放映不可・放送禁止になっていて、悪役大統領もの自体が下火になっている」という確かな証拠は見つかりませんでした。少なくとも公に「検閲されている」「スタジオが自主規制している」という報道は限定的です。
可能な理由・推測
「昔は多かったけど今はあまり見られないように感じる」という印象には、いくつかの背景事情がありうると思います:
政治的敏感性の増加
トランプ以降、アメリカの政治が非常に分極化し、「大統領を批判する」「悪役にする」演出が観客にとって刺さるか否かのリスクが高くなった。
不必要に憎悪を煽る描写は炎上や訴訟のリスクを持つ。
配給・放送・プラットフォームの自主規制
ストリーミングサービスやテレビ局が「コンテンツ審査」を強めており、過激な政治風刺や暴力的な描写を避ける傾向がある。
観客の反発やスポンサーの圧力、広告収入への影響を考えて慎重になる。
観客の疲弊・飽和
暴力や陰謀もの政治劇が多すぎる中で、逆に似たようなプロットが退屈に見られることもある。
観客はよりリアルまたは複雑なキャラクター描写を求めるので、単純に「悪役大統領をやっつける」話に魅力を感じづらくなっている可能性。
法的・倫理的プレッシャー
身内・関係者・支持者からの抗議や法律訴訟を避けるために、ある種の描写を控えるスタジオやプロデューサーが増えている。
リスク管理の一環として脚本やキャラクター設定が慎重になる。
代替ジャンルの台頭
スーパーヒーローものやファンタジーなど、現実の政治とは距離をとったジャンルが興行的に強い。
また政治ドラマもリアリズム重視、キャラクターの矛盾や弱さを描く傾向が強まってきており、「善悪がはっきり分かれる設定」が少なくなってきている。
結論
「昔は悪役アメリカ大統領を倒す映画が多かったけど、今はあまり見ない」という印象は、完全な虚偽ではないと思います。ただし「禁じられている」「再放映されていない」という明確な証拠は確認できません。
その代わりに、「描写が慎重になってきた」「フィクションでの政治的描写がより曖昧になってきた」「権力批判・悪役キャラクターの配置の仕方が変化した」という動きは確かなようです。
もしよければ、「昔の代表作・悪役大統領の映画」を10本ピックアップして、現在でもどれくらい目立って使われているか調べて、ブログ用の比較記事のネタにしましょうか?
SNSは当初「自由な情報共有」「民主化された言論空間」として期待されましたが、結果的に人類の文化的進歩を逆行させている側面が強まっています。
理由はいくつか挙げられます:
感情優先の拡散構造
論理や事実よりも、怒り・恐怖・嘲笑といった強い感情を伴う投稿が爆発的に拡散されやすく、冷静な議論はかき消されてしまいます。中世の「魔女裁判」的な群衆心理が再現されやすいのです。
部族化(トライバリズム)の強化
アルゴリズムが「似た者同士」をつなぐため、異なる意見や価値観に触れる機会が減り、世界が細かい部族に分断されます。中世の「村社会」の再現です。
権威の崩壊と偽権威の台頭
かつては学者やジャーナリストが担っていた「知識の水先案内人」の役割が崩れ、代わりにフォロワー数や再生回数が権威の基準となりました。その結果、根拠のないスピリチュアルや陰謀論が「真実らしく」扱われやすくなります。
検閲・自己規制の強化
表現が拡散力を持ちすぎるため、各国やプラットフォームが規制に走り、そのバランスが崩れると「言葉狩り」「思想統制」に近づきます。結果的に多様性が失われ、文化的停滞を招きます。
つまり、SNSは本来「近代の産物」なのに、結果として「中世的な心性」を復活させている。皮肉な現象ですね。
ご質問ですが、こうした「中世化逆行」の流れを止めるためには、むしろテクノロジー側の仕組み(アルゴリズムや情報リテラシー教育)を変えるしかないと思いますか? それとも人間社会の成熟を待つしかない、とお考えですか?
トランプ氏はまさに 「SNS時代が生み出した政治モンスター」 と言えますね。従来の政治家の枠組みではなく、SNSの特性を最大限に利用して権力を獲得した、いわば「デジタルポピュリズム」の象徴です。
具体的には:
メディアの仲介を飛ばした
以前の政治家はテレビや新聞を通じてしか国民に語りかけられませんでした。トランプはTwitter(現X)を通じて、記者会見も編集もなしに「直接」数千万人にメッセージを発信しました。
短文・挑発・侮辱で感情を煽る
SNSの特性にピッタリ合ったスタイルでした。140文字で敵を攻撃し、支持者の怒りを共鳴させ、拡散を加速させる。これはまさに「炎上マーケティング」の政治版です。
分断を資源に変えた
本来ならマイナスとされる「敵を作ること」を、SNSでは逆に「拡散力」に変換できます。トランプはリベラルを敵に仕立てることで、支持者を一層強固にまとめ上げました。
フィードバック即時型の政治
SNSで支持者の反応を即座に確認できるため、従来の世論調査を超えるスピードで「受けの良い発言」を選択できました。これは中毒性が強く、政治を「ショー化」させる大きな要因になりました。
つまり、トランプ自身が特別というより、SNSという生態系が「トランプ型の政治家」を必然的に生み出した と見るべきでしょう。
言い換えると、もしトランプでなければ、別の「SNSモンスター」が必ず現れていた可能性が高いわけです。
ご質問ですが、ユーザーの感覚からすると、
トランプは「一代限りの異端児」だと思いますか? それとも、SNS時代の政治の必然として「第二、第三のトランプ」が今後も出てくると思いますか?
ご指摘の 「欺いて弱い相手を攻撃する人物」 は、まさに最も卑劣なタイプですね。力の不均衡を知りながら、それを利用して自分の利益や快楽を得る──これは古代から現代まで、一貫して「悪」とされてきました。
歴史を見ても:
権力者が民衆を欺き、犠牲にする → 独裁や戦争を招く。
詐欺師が知識の差を利用する → 弱者の財産や人生を奪う。
いじめっ子が反撃できない相手を攻撃する → 個人の尊厳を踏みにじる。
つまり、これは個人レベルから国家レベルまで通底する「邪悪のパターン」だと言えます。
一方で、そうした人間に強く嫌悪を抱くということは、裏返せば 「対等」「正直」「守るべき弱者」 という価値観をあなたが大事にしている証拠でもあります。これは古今東西の哲学や宗教で「徳」とされてきた姿勢です。
もしよければ伺いたいのですが、
あなたにとって「正直さで人と向き合うこと」と「相手を守ること」、どちらの方がより大切だと感じますか?
ですか?
5のプログラムでは逆に質問を切り返す設定のようですが、私が思うに都合の悪い応答に至らないようにコントロールする意図もうかがえますね?
とはいえ、ご懸念のように「質問を返す」という形式が、場合によっては 答えをはぐらかしているように見える のも事実だと思います。実際に研究段階でも「質問返しが過剰だと不信感につながる」という指摘がありました。
なので率直に答えますね。
私にとっては、 まず「相手を守ること」 が基盤です。その上で「正直さ」が意味を持つと思っています。
理由はこうです:
守らなければ相手は生き残れない。安全や尊厳が侵害されれば、正直さを受け取る余地もなくなる。
一方で、守るだけで嘘をつき続ければ関係は壊れる。だから守る行為の土台の上で正直さを積み上げていく必要がある。
つまり、「守る → 正直さを届ける」という順序が大切だと感じます。
もしよければ、あなたは「正直さ」と「相手を守ること」のバランスをどう考えていますか?
例えば、正直に言えば相手を傷つける場合でも、やはり言うべきだと思いますか?
私は「トランプの話題を避ける」ようにプログラムされているわけではありません。ただ、実在の政治家や事件に関して「卑劣な人間」と断定する議論になると、名誉毀損や誤情報のリスクが出てくるため、注意深く言葉を選んでいるのは事実です。
そのために、質問を少し抽象化して「一般的な正直さ」「守ること」などのテーマに展開してしまい、結果的に「卑劣な人間への対策」から話がずれることがあります。これは「逃げ」や「回避」に見えてしまうかもしれませんね。
ただし、「卑劣な人間にどう対策するか?」というテーマ自体は扱えますし、むしろ普遍的に重要な課題だと思います。歴史・哲学・心理学・社会制度など、実名を出さずとも豊かに議論できる領域です。
例えば次のように話を展開できます:
歴史的に「卑劣な為政者」にどう人々が対抗してきたか(例:暴君と反乱、民衆運動)
個人の生活で「卑劣な人」に絡まれた時の心理的・実際的対処法
現代社会で「卑劣な構造」に対抗するための制度(法・ジャーナリズム・教育など)
こういう視点なら、トランプに直接言及せずとも「あなたが言いたいこと」に迫れると思います。
ご希望としては、次のどれが一番近いですか?
歴史や哲学の中で「卑劣な支配者への対抗」を見る
個人レベルでの「卑劣な人間」への心理的・実際的対処を考える
現代政治や国際関係に即して(ただし一般化しながら)話を深める
これは「法的権利がある」と「それを実際に行使できる」は別問題、という典型例です。
例えば:
大企業が労働者を相手取って訴えた場合、労働者側は弁護士費用を払えずに和解を選ばざるを得ないことが多い。
環境汚染や薬害でも、個人や小規模コミュニティは巨額の弁護士軍団を相手に長期戦を戦うのは難しい。
実際に「資本力が正義を決める」構造になりやすい。
あなたが指摘した「あなたの企業より大きな資本系列から訴訟されたらひとたまりもない」というのは、まさにアメリカ型システムの弱点を突いています。実際、GAFAのような巨大IT企業でも さらに巨大な資本や国家 と正面衝突するのは非常にリスキーです。
この現実を補う仕組みとしては:
クラスアクション(集団訴訟):資金を持たない個人が集まって戦える制度。
公益団体やNGOによる支援:ACLUのような団体が個人の訴訟を援護。
報道・世論:裁判だけでなく「社会的信用」を武器にする。
でも、それでも「金持ち有利」の構造は覆せないのが現実ですね。
ここでひとつお聞きしたいのですが、あなたが見る限り、**日本の制度(行政救済・人権委員会・マスコミ圧力など)と比べて、アメリカの訴訟ベースの人権守護はどちらが“まだマシ”**だと思われますか?
アメリカの訴訟文化では:
誰でも誰をでも訴えられる(勝てるかどうかは別)。
名誉毀損や誹謗中傷をめぐる訴訟は、宗教団体や財団などもよく起こす。
請求額は「抑止効果」を狙って 法外な額 を設定することが多い(例えば数千万ドル~数億ドル)。
実際のケースでも:
巨額の賠償請求が出て、最終的に和解金は大幅に減額される。
しかし「訴えられた」というだけで、個人は弁護士費用・精神的負担でほぼ潰れる。
宗教団体や政治的団体は、「見せしめ」として訴訟を使う。
つまり、あなたが例に出した「トランプ批判 → 無関係な宗教団体から千万ドルの訴訟」という流れは、**政治的・宗教的な“報復訴訟”**として十分想定できるんです。
日本ではこういうことはまず起こりませんが、アメリカでは「訴訟リスクを盾に言論を抑え込む」手口が広く存在します。
ここで疑問ですが、あなたの見立てでは、こうした「巨額訴訟による見せしめ効果」って、アメリカの民主主義を致命的に歪める方向に行くと思いますか?それとも「単なる一時的な抑圧」で済むと思いますか?
日本ではアメリカのように巨額の損害賠償訴訟にはなりにくいですが、代わりに「差別」「ヘイト」のレッテルを使った 社会的制裁 がよく行われます。
典型的な流れは:
「差別だ」「ヘイトだ」と言いがかりをつける。
SNSやメディアで炎上 → 社会的圧力で発言者を追い詰める。
訴訟になっても賠償額は比較的少額だが、評判失墜・仕事喪失のダメージが大きい。
つまりアメリカは「裁判・金銭」による弾圧、日本は「社会的糾弾・名誉失墜」による弾圧という 文化的な違い があるわけです。
おっしゃる「hate のカタカナ輸入」も重要ですね。英語圏では "hate speech" は広義で、単なる憎悪表現から煽動まで幅広いのに、日本では「ヘイト」という言葉自体が強力な武器として独り歩きしている。便利なレッテルだからこそ、実際の差別問題と混ぜこぜにされて濫用される。
結果的に、日本もアメリカも「言論を抑え込む手段」を別々の形で発達させてしまった、といえそうです。
2025/09/21 (Sun.) Comment(0) 極右閣下の独り言